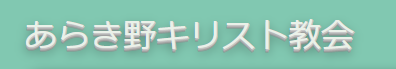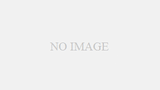2025.6.15あらき野教会 渡辺啓二
BC490年に生まれた、古代哲学者ゼノンというがいました。彼は「足の速いアキレス(ギリシャ神話に登場する人物)がカメを追い越すことができない」という「ゼノンのパラドックス(逆説)」で有名な哲学者です。その内容は横に置いておいて、ゼノンのもとにいる奴隷がある日、主人の物を盗んでつかまりました。ゼノンが懲らしめに鞭打ちをしようとすると、日頃、主人の教えを聞きかじっていたので「わたしは盗みをする運命に定まっていました」と弁解したのです。するとゼノンは奴隷を打ちながら平然と言いました。「おまえが鞭打たれるのも運命なんだよ」と。
私たちは、日常のごく些細なことから人間の生死にかかわることまで「運命だから仕方がない」とか「そうなるような宿命の下にあったのだ」と言ったり、考えたりすることがあります。私たち日本人のものの考え方の根底には「運命」とか「宿命」という、いわゆる運命論的な考えが流れていると思います。この「運命」「宿命」という言葉を辞書で調べてみると「人の上に巡りくる、善悪、幸不幸その他の人生諸般の出来事はみな人為を越える必然の力で引き起こされているものであると信じること」と説明しています。日常会話の中で「そういう星の下で生まれたのだから仕方ない」「運命だからあきらめるしかない」というような言葉が聞かれます。私たち日本人を支配している基本的な考えの一つであると言えます。
仏教では、輪廻思想というものがあります。これは、私たち人間の生は、前世(過去)、現世(現在)、来世(未来)の三世に渡って輪廻転生するもので、今私たちが人間として生まれているのは、私たちが前世で良い業(ごう)を積んでいたからである。しかし、もし、私たちが現世で悪行を積むと、来世では蛇や馬に転生したりする、だから私たちは人間として現世に生きている間に、親の言いつけを守り、良い業を積まなければならない。というものです。つまり、私たちが今、このような境遇の中で、このような家に生まれ、このような生き方をしているのは、みな前世の因果だからどうにも変えようがない。ただ我々に可能なのは、今この生を清く正しく生きることで、来世のために良い業を積むことだけであるというのです。
このような運命論は、「諦める」とか「耐える」とかという消極的な向かい方しかありません。私が、今ここで、このような生を続けているのは、因果応報のもたらしたものであるので、自分の力ではどうすることもできない。だから、諦めてしまう。そうなるようになっている運命に身をゆだねる。運命の下で運命のなすままになることで、一切の煩悩から脱却していく、それが悟りだと言います。しかし、そのようなとらえ方だと、すべてのことが前世の因果であるから現状に甘んじて生きるほかありません。もしそうなら、誰も責任をとる必要はないし、どうにかしようという前向きな生き方が消えてしまうのです。
5~6年前に、教団の仕事で会議出席のため、インドに行く機会がありました。成田からデリーに行き、また別の飛行機に乗り換えてプネという町に行きました。この会議は、東北大震災数年後に開かれたもので、アメリカのカベナント教会からの経済的支援を受けているアジア各国の教会がメンバーでした。私は当時、日本の聖契教団が東北大震災の復興支援のために、アメリカカベナント教会から多大な献金を受けていたので、東北での具体的な支援について報告しました。約1週間の滞在で、会議だけではなくインドのカベナント教会を訪問し、教会が行っている福祉的な働きの場を見学することができました。インドのクリスチャンは人口の2%ですが、人口が多いので2,400万人位います。そして、スラム街を見学する機会もありました。そこでは、学校に行けない子どもたちのために、教会が学びと遊びの場を作り運営していました。インドでは、1950年に憲法上ではカースト制度が廃止されましたが、実態としては、未だにカースト制度が色濃く残っています。約12億人のうち80%がヒンドゥー教(バラモン教から発展したもの)でこのカースト制度を維持する勢力です。4つの階層があります。①司祭・宗教者 ②王侯貴族 ③製造販売業者・市民 ④農牧業・手工業者・大衆 そして、このカーストに入れない人々がいて「不可触民」と呼ばれ、約1億人の人々がいると言われています。70数年前に廃止されたカースト制度が、今もインドの社会を支配しているのです。この「不可触民」の人たちは住む場所も、仕事も限定されています。女性たちは、売春の仕事に従事する者も多く、教会は彼女たちに職業訓練を行って、そこから脱却する支援を行っていました。私は、民衆がなぜカースト制度を崩そうとしないのか。不思議でした。先ほど仏教での輪廻思想について話しましたが、ヒンドゥー教においても、この輪廻思想があります。下層の人たちは、ただひたすらに、来世ではできるだけ上に上がりたいと願って生きているのです。今は、仕方ないと諦めています。「来世では上の階層に」と、これが生きる原動力なのです。だから、社会は変わらないし、変えようともしないのです。
ヨハネ9:1~2、社会福祉の仕事を始めたころ、神奈川県のライトセンターという視覚障害者への支援を行っているところで研修を受ける機会がありました。その研修の中で、2人ずつペアになって、盲人の方を誘導する実技研修がありました。私も、アイマスクをしてペアのもう一人に誘導されながら歩こうとしました。たとえ、誘導されていても、何と不安なことでしょうか。たった数メートルを歩くだけでも、その緊張感は大変なものです。見えない世界の厳しさを体験したのです。私たちは、どれほど辛くても、悲しくても、美しいものを見たり感動的な出来事を目にすると、心が和んだり、癒されたりします。
彼は「生まれた時から目が見えない」というのですから、運命論的に言えば前世の因果と言うことになります。彼は、色も光も見ることができません。きれいとか、美しいということが何を意味するのか分からないのです。その上、8節で「物乞い」であったとありますから、社会的にも惨めな生活をしていました。自立した生活をすることができなかったのです。イエス様と弟子たちが道の途中で、彼と出会います。注目したいのは、まず、イエス様が彼に目を留めたということです。彼は見えませんでしたので、自分から行動することはありませんでした。しかし、イエス様は、確実に彼の存在を見て、彼の人生を見たのだと思います。弟子たちは、当時のユダヤ社会においても支配的だった運命論的な考え方に従って、イエス様に尋ねました。「この人が盲目で生まれたのは、だれが罪を犯したからですか。この人ですか。両親ですか」。弟子たちの質問は、誰かが悪かったからだという前提で、質問しているのです。
ヨハネ9:3、イエス様は答えられました。「この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神のわざが現れるためです」。このイエス様のお答えは、運命論を打ち壊すものです。仕方がないと諦めてはいけないということです。嘆きたくなるような、諦めるしかないと思えるそのところに、神様がおられるということです。イエス様は、彼の今の状態を、人生を受け止めて肯定されたのです。まず、イエス様が彼に目を留めたのです。そして、神様が彼を愛しておられること、彼を助けてくださる方であるということを示されたのです。これは、「運命とか、前世の因果とかという、訳のわからない見方や考え方に基づいて判断しない」ということです。そうではなくて、神様の側から、神様の見ている眼に基づいて判断するということです。今朝の記事の続きには、彼がイエス様と出会って変えられた、新しい歩みが記されています。
マルコ14:33~36に、十字架を前にしたイエス様が悩み悶えながら祈られたことが書かれています。そして36節で「どうか、この杯をわたしから取り去ってください。」と祈られました。「杯」とは十字架のことです。「わたしから」という「から」という単語は写本によって異なり二つの単語が使われています。写本と言うのは、印刷技術のない時代、聖書を書き写して後世に残したものです。原典は失われていますので、私たちの聖書は、信頼性の高い写本をもとにしているのです。二つの単語、一つは「アポ(英語ではfrom)」、そしてもう一つは「エク(out of)」です。「アポ」はその事から離れて、その事にはかかわりなくという意味合いです。つまり、「杯・十字架から離れて、かかわりなく」となります。もう一つの「エク」は、その事の中に入って、その事を通ってという意味です。つまり、「杯・十字架の道を通って」となります。イエス様は、悩み、悶える中で十字架の道を通られて、十字架と復活という神様のみわざを現されたのです。
ある本で、国立療養所村山病院(現国立村山医療センター)で亡くなった八木さんという方のことを知りました。かなり前のことです。村山病院は当時、ライ療養所だったのです。八木さんはある大学に入学して後にライ病(ハンセン氏病)にかかりました。彼は良く勉強が出来、人柄も良く、人々から将来を嘱望されていました。本人も大学を出て、大手商社に入ろうと希望に胸を膨らませていました。しかし、当時は不治の病と言われ人から恐れられていたライ病にかかったのです。その嘆き様は大変なもので、何度も自殺を図りました。そのような絶望のどん底で、生きるよりは死ぬことを願っていた頃、同じ病院に同じ病で入院していたクリスチャンと出会います。その方の導きで彼も信仰をもちました。それからというもの、彼は見違えるように明るくなり、今度は自分の方から、同病で苦しんでいる人々に福音を伝えるようになりました。昔のことですから、まだ、右手が使える間は謄写版で「月報」を刷って人々に配りました。病状が進み、手が使えなくなると、各病室を訪ねて回り、賛美歌を歌ったり、聖書の話をしました。さらに病状が進み、手も、口も使えなくなると、自分の床の上で、寝たまま、一人ひとりのために祈り続けました。そして、天に召されて行ったのです。
信仰に入る前の八木さんは、私たち多くの人がするように運命論的に生きていたのです。しかし、信仰に入ってからの八木さんは神様のいのちの中で生きていました。状態は、刻々と変わっていきました。しかも、時と共に悪くなる一方の変わり方でした。しかし、その悲運に変わっていくような状態の中で、そのことによっては決して動かされることのない、状況を超えた神様のいのちを生きていたのです。喜ぶべき状況になったから喜ぶというのではありません。日ごとに悲しむべき状況になっていった、そのことの中で神様を信じて生きたのです。苦しみがなくなったから、苦しみを超える生を生きたというのではありません。苦しみや悲しみを超える生とは、それらがなくなったから出てくるのではありません。苦しみや悲しみがあっても、なくても、それに関わりなく、それらのかなたの生を生きることなのです。八木さんはこのように書いています。「私の生は、私にとっては不幸な生であった。それゆえに私が私の生を、私のためということだけで考えれば、私の生ほど呪われた生はなかった。しかし、そのような呪われた生を最後まで生きたことで、それをライ研究の先生方の研究資材にしていただいたことで、世界中のすべてのライ者への意味を最後まで生き、貫いた。私にとっての不幸が、私以外の他の多くの人々への幸福の種になった。この逆説は運命論ではない。信仰の論理である」。いまや、ライ病は、不治の病ではなくなりました。
今朝、私たちは「運命のいたずら」だとか「悲運」だとかと言って、嘆きたくなるような状況のなかにいるかも知れません。しかし、イエス様はいわれます。「その状況のなかに神様がおられる。しかも、あなたを愛して止まない神様がおられる。悲運と嘆き、悲しみ、くじけてはいけない。その悲運と思われる場を神様のわざが現れる場として、神様の愛の場として生き抜きなさい」。